更新日:2025年8月22日
ここから本文です。
イノシシの生態と自己防衛策
イノシシによる被害

近年、イノシシ等の鳥獣による被害は全国的に深刻化しているのが現状です。
イノシシはエサを求めて行動します。鼻を使って土を掘ったり石を持ち上げたりして手当たり次第にエサを探します。その結果、次のような被害をもたらします。
- 栽培している農作物を食べる。
- 花壇を掘り起こす、植木鉢や庭の縁石を引っくり返す。
- 裏山や崖などを掘り、大穴をあけたり、土や石を落とす。
残念ながら、すべての鳥獣被害防止に絶対的に有効な対策はありません。
まずは、自己防衛をしてください。
防止対策の効果を上げるポイントは、下記のとおりです。
- 野生鳥獣の習性を知ること
- 来にくい環境を作ること
- 対策を根気よく続けること
イノシシの特性と対策についてまとめてみましたので、参考にしてください。
イノシシの生態と習性
性格
イノシシの警戒心はとても強く、本来人前に姿を現す動物ではありません。
臆病な性格から環境の変化に敏感で、ちょっとした変化に警戒心を抱きます。
一方で大胆な面もあり、単なるおどしにはすぐに慣れてしまいます。
記憶力は高く、学習したことは半年以上記憶しているため、一度「エサ場」と記憶した田畑には何度でも侵入します。
体力
大きくなったイノシシは体重が100キログラムを超え、オスは大きな牙が出ます。またメスは一年に一度、平均4頭から5頭の子どもを産むため、繁殖力が旺盛です。
運動能力や学習能力も高く、成獣では助走なしに120センチメートル(1歳未満の子イノシシで70センチメートル)ジャンプすることもできますし、50キログラムのものを鼻で持ち上げることもできます。
被害の特徴
イノシシの好物はサツマイモやスイカ、稲、果物などの農作物や、昆虫の幼虫、ヘビ、ミミズなどですが、雑食性で家庭の残飯なども食べます。
イノシシは田畑に侵入し、農作物を食い荒らします。
特に土の中の物が好物なため、鼻で地面を掘り起こし、大きな穴をあけることがあります。田へは稲の穂が出揃った頃、集団でやってきて穂を食い荒らし、泥浴びをしたりするため、一晩で稲が全滅することもあります。また石垣を崩したり、水路を埋めたりすることがあり、土砂災害の原因となることがあります。
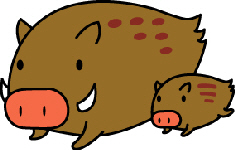
イノシシに出会ったら
イノシシは本来、臆病でおとなしい性格のため、人に出会ってもイノシシの方から逃げてしまいます。
しかし、興奮していたり、発情期(晩秋~冬)や分娩後で攻撃的になっていたり、至近距離で出会った場合には注意が必要です。
落ち着いてゆっくり行動
イノシシに出会ったら、静かにその場を離れましょう。
急に走り出したり、後ろを向いて逃げたりせず、なるべく背中を見せずにゆっくりと後退しましょう。
攻撃したり刺激しない
興奮状態のイノシシに、棒を振り回す、石を投げるなどの攻撃は逆効果です。
下手に刺激することは避けてください。
うり坊には近づかない
うり坊(イノシシの子)は、近くに母イノシシがいる可能性が高いので、近づかないでください。
餌やりなども、人を食べ物の供給源だと学習してしまう危険性があるので控えましょう。
どうしても逃げられない場合
人間がいる方向以外に逃げ場がない場合は、イノシシが接近してくることもあります。
その場合は、イノシシに逃げ道を明け渡しつつ、イノシシから見えない場所や簡単に登れない立木などに登り、緊急避難をしてください。
【対策1】地域ぐるみで鳥獣のエサになるものを取り除く
故意の「餌付け」でなく、知らないうちに行っている「無意識の餌付け」について再点検し、イノシシを呼び寄せない環境づくりをしましょう。
- 稲刈り後の水田はなるべく早く田を耕す。(落穂・2番穂を出さない)
- 収穫残さを田畑に捨てない。
- 田畑の農作物は残さず収穫をする。
- 田畑や周辺に雑草を繁茂させない。
【対策2】防止対策のいろいろ
|
種類 |
効果と弱点 |
設置方法 |
|---|---|---|
|
トタン板 |
目隠し効果もあり、侵入を防ぐ。 飛び越える、押し倒す、鼻で持ち上げるなどして、侵入する可能性あり。 |
廃材など強度のある支柱を使い、土地の起伏に合わせて、裾や合わせ目に隙間ができないように設置する。 |
|
ネット |
クッション効果によって、金網より侵入しにくいが、イノシシは食い破り侵入することがある。 |
支柱を立てて外側に1メートルほど垂らす。設置面をくぐり抜けしないようにしっかり固定する。 |
|
金網格子 |
目隠し効果はあるが強度が弱い、下からくぐりぬけて侵入することがある。 |
設置面をしっかり固定して、くぐり抜けできないように設置する。 |
|
電気柵 |
効果は非常に高いが、失敗例もある。 侵入獣が電気ショックに驚いて瞬間的に走り出し、侵入だけでなく資材を破損する場合がある。 |
作物から距離をとって柵を設置する。電線は、獣の感電部の高さとする。イノシシは20センチメートルで2段から3段、シカは4段を目安とする。 |
自己防衛をしても被害を防ぐことができない時は・・・・・【対策3】へ
【対策3】鳥獣の捕獲
野生鳥獣は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟に関する法律」で保護されており、捕獲をすることは基本的に禁止されています。
イノシシは、狩猟鳥獣ですので静岡県に狩猟登録済みの者に限り狩猟期間中の捕獲が可能です。また、狩猟期間以外でも鳥獣による農作物等の被害が大きい場合には、被害防止目的(有害鳥獣)捕獲として捕獲を許可することができます。
被害防止目的(有害鳥獣)捕獲は、市への申請が必要となりますので詳細は、農林課にお問い合わせ下さい。
捕獲に必要な銃や罠を使用するには、「特別な資格」が必要となります。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください